月例経済報告 令和7年9月 ー個人消費・設備投資・企業収益の変化と今後の見通しー

令和7年9月の月例経済報告が公表されました。今月も景気の基調判断は「緩やかに回復している」とされ、全体としては安定したトーンが維持されていますが、個別項目に目を向けると、先月からの変化が随所に見られます。特に「個人消費」「設備投資」「企業収益」「国内企業物価」の4項目においては、表現や統計数値に微妙な変化があり、景気の足取りをより丁寧に読み解く必要があります。
米国の通商政策の影響が自動車産業を中心に顕在化している点や、物価の動向が企業活動に与える影響など、外部環境の不確実性も引き続き注視すべき要素です。今回のブログでは、令和7年8月と9月の月例経済報告を比較しながら、特に変化が見られた4項目について詳しく解説します。統計データの裏にある実態や、先行きに対する見通しを読み解くことで、今後の経済動向をより深く理解する一助となれば幸いです。
この記事を読んで分かること
- 景気は緩やかに回復しているが、外部リスクに注意が必要
- 個人消費は雇用環境の改善を背景に持ち直し傾向
- 設備投資は製造業が牽引し、全体として緩やかに回復
- 企業収益は製造業が減益、非製造業・中小企業は堅調
- 国内企業物価は下落に転じ、価格の停滞感が強まる
1.令和7年9月分について
(1)主要な項目
主要な項目を、令和7年8月、令和7年9月について、以下掲載します。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 | |
| 基調判断 | 景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している | 景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心 にみられるものの、緩やかに回復している |
| 個人消費 | 消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
| 設備投資 | 持ち直しの動きがみられる | 緩やかに持ち直している |
| 住宅建設 | 建築物省エネ法等改正に伴う駆け込み需要の反動もあり、このところ弱含んでいる | 建築物省エネ法等改正に伴う駆け込み需要の反動もあり、このところ弱含んでいる |
| 公共投資 | 堅調に推移している | 堅調に推移している |
| 輸出 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 輸入 | 持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
| 貿易・サービス収支 | 赤字となっている | 赤字となっている |
| 生産 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている |
| 企業収益 | 米国の通商政策等による影響が一部にみられる中で、改善に足踏みがみられる | 米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる |
| 業況判断 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 倒産件数 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 雇用情勢 | 改善の動きがみられる | 改善の動きがみられる |
| 国内企業物価 | このところ上昇テンポが鈍化している | このところ横ばいとなっている |
| 消費者物価 | 上昇している | 上昇している |
個人消費、設備投資、企業収益、国内企業物価の表記に変化がある。
今月も随分と記述に変化が見られました。
以下、記述に変化のありました個人消費、設備投資、企業収益、国内企業物価について詳しくみていきます。

(2)個人消費
①令和7年8月と令和7年9月の比較
令和7年(2025年)8月と9月の詳細を、以下記載します。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 |
| 個人消費は、消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 「四半期別GDP速報」( 2025 年4-6月期1次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比0.2%増となった。 また、「消費動向指数(CTI)」(6月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比0.1%増となった。 個別の指標について、需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(6月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、総世帯)の実質値は前月比2.2%減となった。 供給側の統計をみると、「商業動態統計」(6月)では、小売業販売額は前月比0.9%増となった。 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。 また、消費者マインドは、下げ止まっている。 さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直している。 家電販売は、持ち直している。 旅行は、おおむね横ばいとなっている。 外食は、緩やかに増加している。 こうしたことを踏まえると、個人消費は、消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。 | 個人消費は、持ち直しの動きがみられる。 「四半期別GDP速報」(2025 年4-6月期2次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比 0.4%増となった。 また、「消費動向指数(CTI)」(7月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比0.0%増となった。 個別の指標について、需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(7月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、総世帯)の実質値は前月比 0.8%増となった。 供給側の統計をみると、「商業動態統計」(7月)では、小売業販売額は前月比 1.6%減となった。 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。 また、消費者マインドは、持ち直しの動きがみられる。 さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直しの動きに足踏みがみられる。 家電販売は、持ち直している。 旅行は、おおむね横ばいとなっている。 外食は、緩やかに増加している。 こうしたことを踏まえると、個人消費は、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。 |
個人消費は雇用・所得環境の改善を背景に持ち直し傾向。消費者マインドも回復の兆し。
②解説
2025年8月と9月の月例経済報告を比較すると、個人消費の動向には共通する「持ち直しの兆し」が見られる一方で、統計指標の変化や消費者マインドの改善度合いに微妙な違いが浮かび上がります。
まず、GDP速報値に注目すると、8月時点の一次速報では民間最終消費支出が前期比0.2%増だったのに対し、9月の二次速報では0.4%増と上方修正されました。これは個人消費の回復が想定以上に進んでいる可能性を示唆しており、9月報告ではより前向きな評価がなされています。
次に、消費動向指数(CTI)のマクロ指標を見ると、8月(6月分)は前月比0.1%増、9月(7月分)は横ばい(0.0%増)となっており、全体的な消費の勢いはやや鈍化した印象です。しかし、ミクロ指標では対照的な動きが見られます。8月報告では世帯消費動向指数が2.2%減と大きく落ち込んでいたのに対し、9月報告では0.8%増と回復傾向に転じています。これは家計レベルでの消費活動が改善していることを示しており、消費者の購買意欲が徐々に戻りつつあることがうかがえます。
供給側の統計である商業動態統計では、8月(6月分)が前月比0.9%増だったのに対し、9月(7月分)は1.6%減と反転しています。これは小売業の販売額が一時的に落ち込んだことを示しており、消費の回復が一様ではないことを物語っています。
背景要因としては、両月ともに「実質総雇用者所得の緩やかな持ち直し」が共通して挙げられており、雇用・所得環境の改善が消費を下支えしている構図は変わりません。ただし、消費者マインドの評価には違いがあります。8月では「下げ止まり」とされていたのに対し、9月では「持ち直しの動きがみられる」とされており、心理面での改善が進んでいることが読み取れます。
個別消費項目のヒアリング結果も比較すると、家電販売や外食は両月ともに持ち直し傾向にありますが、新車販売台数は8月では「持ち直している」とされたのに対し、9月では「足踏みがみられる」と評価が後退しています。旅行は両月とも「おおむね横ばい」とされ、回復には時間を要している状況です。
総じて、9月報告では統計的にも心理的にも個人消費の回復がより明確に示されており、先行きに対する期待感も高まっています。ただし、消費者マインドの動向には引き続き注意が必要であり、所得環境の改善が継続するかどうかが今後の消費動向を左右する重要なポイントとなります。

(3)設備投資
①令和7年8月と令和7年9月の比較
令和7年(2025年)8月と9月の詳細になります。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 |
| 設備投資は、持ち直しの動きがみられる。 需要側統計である「法人企業統計季報」(1-3月期調査、含むソフトウェア)でみると、2025 年1-3月期は前期比1.6%増となった。 業種別にみると、製造業は同0.1%増、非製造業は同2.4%増となった。 機械設備投資の供給側統計である資本財総供給(除く輸送機械)は、おおむね横ばいとなっている。 ソフトウェア投資は、増加している。 「日銀短観」(6月調査)によると、全産業の2025 年度設備投資計画は、増加が見込まれている。 「日銀短観」による企業の設備判断DIは、6月調査で、製造業では+1と、3月調査(+1)から過剰超幅が横ばい、非製造業を含む全産業では-2と、3月調査(-2)から不足超幅が横ばいとなっている。 先行指標をみると、機械受注は、持ち直しの動きがみられる。 建築工事費予定額は、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、これまでの堅調な企業収益や省力化投資への対応等を背景に、持ち直し傾向が続くことが期待される。 | 設備投資は、緩やかに持ち直している。 需要側統計である「法人企業統計季報」(4-6月期調査、含むソフトウェア)でみると、2025 年4-6月期は前期比 1.6%増となった。 業種別にみると、製造業は同6.3%増、非製造業は同1.0%減となった。 機械設備投資の供給側統計である資本財総供給(除く輸送機械)は、おおむね横ばいとなっている。 ソフトウェア投資は、増加している。 「日銀短観」(6月調査)によると、全産業の 2025 年度設備投資計画は、増加が見込まれている。 「日銀短観」による企業の設備判断DIは、6月調査で、製造業では+1と、3月調査(+1)から過剰超幅が横ばい、非製造業を含む全産業では-2と、3月調査(-2)から不足超幅が横ばいとなっている。 先行指標をみると、機械受注は、持ち直しの動きがみられる。 建築工事費予定額は、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、これまでの堅調な企業収益や省力化投資への対応等を背景に、持ち直し傾向が続くことが期待される。 |
設備投資は製造業が大幅増、非製造業は減少。全体では緩やかな持ち直し傾向が続く。
②解説
2025年8月と9月の月例経済報告における設備投資の動向を比較すると、両月とも「持ち直し」が共通の評価となっているものの、表現や統計の中身には微妙な違いが見られます。8月は「持ち直しの動きがみられる」とされ、9月では「緩やかに持ち直している」と表現されており、回復のペースがやや落ち着いた印象を与えます。
まず、需要側統計である「法人企業統計季報」に注目すると、両月とも前期比1.6%増という同じ伸び率が示されています。ただし、業種別の内訳に違いがあり、8月(1-3月期)では製造業が0.1%増、非製造業が2.4%増と非製造業が牽引していたのに対し、9月(4-6月期)では製造業が6.3%増と大幅に伸び、非製造業は1.0%減と反転しています。これは、製造業の設備投資意欲が高まる一方で、非製造業では慎重な姿勢が見られることを示しています。
供給側統計である資本財総供給(除く輸送機械)は、両月とも「おおむね横ばい」とされており、設備投資の実行段階では大きな変化がないことがうかがえます。一方、ソフトウェア投資は両月とも「増加している」とされ、デジタル分野への投資が継続している点は共通しています。
「日銀短観」(6月調査)に基づく設備投資計画は、両月とも「増加が見込まれている」とされ、企業の先行きに対する前向きな姿勢は変わっていません。また、設備判断DIも製造業が+1、全産業が-2と、3月調査から横ばいであり、過剰・不足感に大きな変化は見られません。
先行指標として挙げられている機械受注や建築工事費予定額も、両月とも「持ち直しの動きがみられる」とされており、今後の設備投資の継続的な回復を示唆しています。
総じて、8月報告では非製造業の投資が活発だったのに対し、9月報告では製造業が主導する形で設備投資が緩やかに回復している構図が見て取れます。企業収益の堅調さや省力化ニーズが背景にあり、今後も持ち直し傾向が続くことが期待されますが、業種間での投資意欲の差や供給側の動向には引き続き注視が必要です。
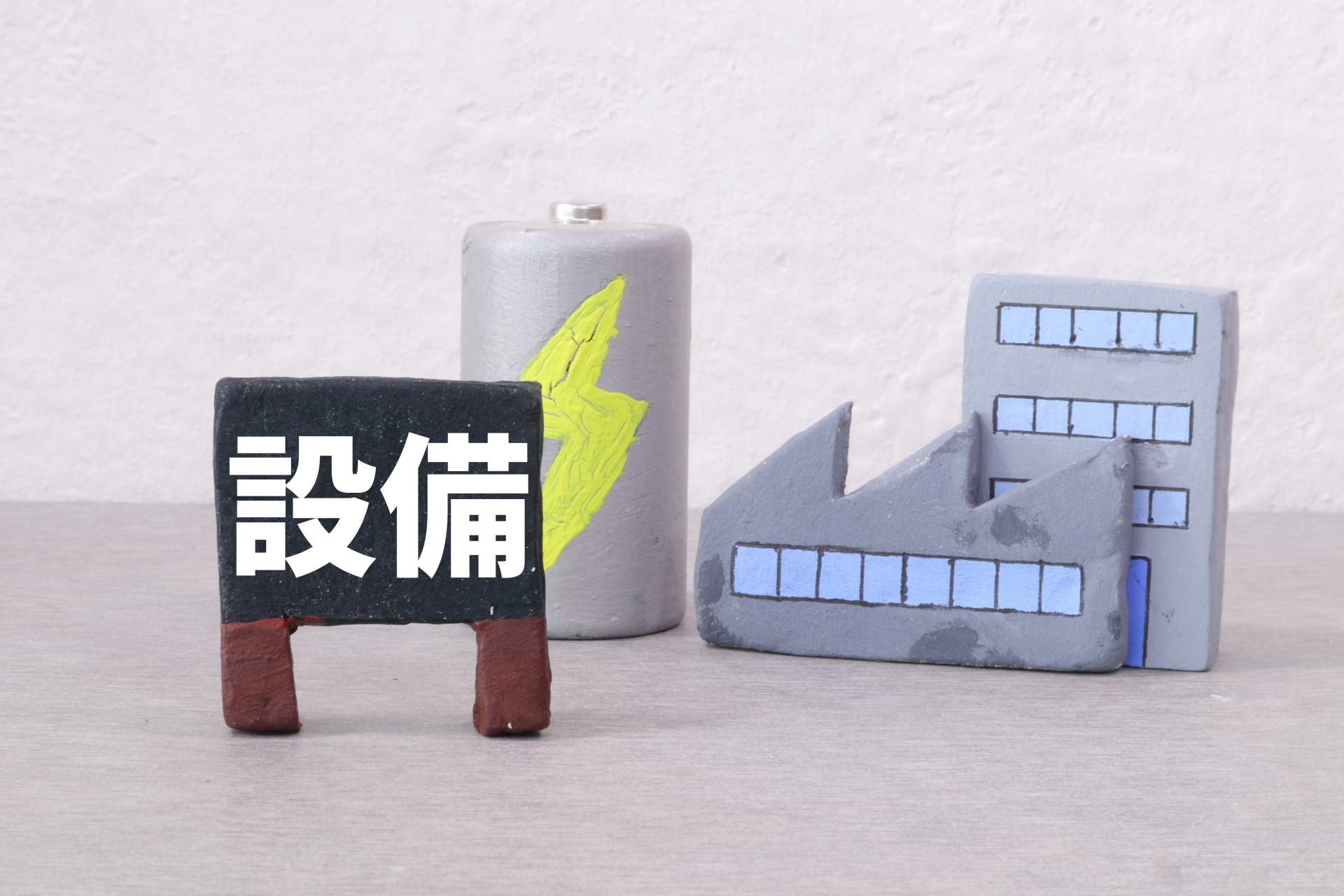
(4)企業収益
①令和7年8月と令和7年9月の比較
令和7年(2025年)8月と9月の詳細です。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 |
| 企業収益は、米国の通商政策等による影響が一部にみられる中で、改善に足踏みがみられる。 上場企業の2025 年4-6月期の決算をみると、経常利益は、製造業、非製造業ともに前年比で減益となった。 「日銀短観」(6月調査)によると、2025 年度の売上高は、上期は前年比1.9%増、下期は同0.9%増が見込まれている。 経常利益は、上期は前年比4.5%減、下期は同6.9%減が見込まれている。 | 企業収益は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる。 企業収益は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる。 「法人企業統計季報」(4-6月期調査)によると2025年4-6月期の経常利益は、前年比0.2%増、前期比0.7%増となった。 業種別にみると、製造業が前年比 11.5%減、非製造業が同6.6%増となった。 規模別にみると大・中堅企業が前年比1.0%減、中小企業が同6.0%増となった。 「日銀短観」(6月調査)によると、2025年度の売上高は、上期は前年比1.9%増、下期は同0.9%増が見込まれている。 経常利益は、上期は前年比4.5%減、下期は同6.9%減が見込まれている。 |
企業収益は改善に足踏み。製造業は減益傾向、非製造業や中小企業は堅調な動き。
②解説
2025年8月と9月の月例経済報告における企業収益の動向は、いずれも「改善に足踏みがみられる」と評価されており、回復の勢いが鈍化している状況が続いています。特に、米国の通商政策の影響が両月ともに指摘されており、外部環境の不確実性が企業収益の重しとなっていることがうかがえます。
8月報告では、上場企業の2025年4-6月期決算において、製造業・非製造業ともに前年比で減益となったことが示され、企業全体の収益環境に厳しさが見られました。これに対し、9月報告では同期間の「法人企業統計季報」に基づく経常利益が前年比0.2%増、前期比0.7%増と、わずかながら改善が見られたことが強調されています。これは統計の対象や集計方法の違いによるものと考えられますが、企業収益の底堅さを示す材料とも言えます。
業種別に見ると、8月では製造業・非製造業ともに減益だったのに対し、9月では製造業が前年比11.5%減と大きく落ち込む一方、非製造業は6.6%増と好調を維持しています。特に自動車産業が米国の通商政策の影響を受けている点が9月報告で明記されており、製造業の収益悪化の一因となっていることが読み取れます。
企業規模別では、9月報告において大・中堅企業が前年比1.0%減、中小企業が6.0%増と、規模によって収益の差が顕著に現れています。これは中小企業が比較的内需に依存していることや、コスト構造の柔軟性などが影響している可能性があります。
「日銀短観」(6月調査)による売上高・経常利益の見通しは、両月とも同じ内容が示されており、2025年度の売上高は上期1.9%増、下期0.9%増と緩やかな増加が見込まれています。一方、経常利益は上期4.5%減、下期6.9%減と、収益面では厳しい見通しが続いています。これは原材料価格の高止まりや為替変動、海外市場の不透明感などが影響していると考えられます。
総じて、企業収益は改善の兆しが見られるものの、外部環境の影響や業種・規模によるばらつきが大きく、力強い回復には至っていない状況です。今後の動向を見極めるには、通商政策の変化や国内外の景気動向に加え、企業のコスト管理や収益構造の変化にも注目する必要があります。

(5)国内企業物価
①令和7年8月と令和7年9月の比較
令和7年(2025年)8月と9月の詳細です。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 |
| 国内企業物価は、このところ上昇テンポが鈍化している。 7月の国内企業物価は、前月比0.2%上昇し、夏季電力料金調整後では、前月比0.1%上昇した。 輸入物価(円ベース)は、おおむね横ばいとなっている。 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。 | 国内企業物価は、このところ横ばいとなっている。 8月の国内企業物価は、前月比 0.2%下落し、夏季電力料金調整後でも、前月比 0.2%下落した。 輸入物価(円ベース)は、おおむね横ばいとなっている。 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、このところ上昇テンポが鈍化している。 |
国内企業物価は上昇から横ばいへ。8月は下落に転じ、価格の停滞感が強まる。
②解説
2025年8月と9月の月例経済報告における国内企業物価の動向を比較すると、物価の上昇圧力が弱まり、停滞感が強まっている様子が明らかになっています。8月時点では「上昇テンポが鈍化」とされていたのに対し、9月では「横ばい」と評価されており、企業物価の動きがさらに落ち着いてきていることが示唆されています。
具体的な数値を見ると、7月の国内企業物価は前月比0.2%上昇、電力料金調整後では0.1%上昇と、わずかながらも上昇が続いていました。しかし、8月の物価は前月比0.2%下落、電力料金調整後でも同じく0.2%下落となり、明確なマイナスに転じています。これは、エネルギー価格や原材料価格の落ち着き、あるいは需要の鈍化が背景にある可能性があります。
輸入物価(円ベース)は、両月とも「おおむね横ばい」とされており、為替レートや国際市況の安定が反映されていると考えられます。輸入物価が大きく動かないことは、国内企業物価の安定にもつながっており、外部要因による価格変動が抑制されている状況です。
企業向けサービス価格の動向については、8月では「緩やかに上昇している」とされていたのに対し、9月では「上昇テンポが鈍化している」と評価が変化しています。これは、サービス分野においても価格転嫁の余地が限られてきていることを示しており、企業の収益環境やコスト構造に影響を与える可能性があります。
このように、国内企業物価は8月から9月にかけて、上昇から横ばい、さらには一部下落へと転じており、物価の勢いが明確に弱まっています。これは、企業にとっては仕入れコストの安定というメリットがある一方で、価格転嫁による収益改善が難しくなるという側面もあります。
今後の動向としては、エネルギー価格や為替の変動、国際的な供給網の状況などが企業物価に影響を与える可能性があるため、引き続き注視が必要です。特に、物価の停滞が長期化する場合、企業の価格戦略や投資判断にも影響を及ぼすことが考えられます。

2.先行きについて
先行きについては、以下のとおりです。
| 令和7年8月 | 令和7年9月 |
| 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。 加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。 また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある。 | 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。 加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。 また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。 |
9月は8月と同内容となっている。
9月の記載は、先月と同内容となっています。
3.まとめ
令和7年9月の月例経済報告では、景気の基調判断は先月と同様に「緩やかに回復している」とされ、全体としては安定した見通しが示されました。しかし、個別項目に目を向けると、いくつかの重要な変化が見られます。
まず「個人消費」では、8月時点では消費者マインドの改善に遅れがあるとされていましたが、9月には「持ち直しの動きがみられる」と評価が前向きに変化しました。GDP速報値も前期比0.2%増から0.4%増へと上方修正され、世帯消費動向指数もマイナスからプラスに転じるなど、消費活動の回復が統計的にも裏付けられています。
次に「設備投資」では、両月とも前期比1.6%増と同じ伸び率ながら、業種別では8月に非製造業が牽引していたのに対し、9月では製造業が大幅増、非製造業が減少と構図が逆転しました。これは業種ごとの投資意欲の差を示しており、今後の設備投資の方向性を見極める上で重要なポイントです。
「企業収益」については、両月とも改善に足踏みがみられるとされており、米国の通商政策の影響が自動車産業を中心に顕在化しています。統計上はわずかながら増益傾向も見られますが、製造業の減益が目立ち、非製造業や中小企業が比較的堅調な動きを示しています。
最後に「国内企業物価」は、8月には上昇テンポの鈍化、9月には横ばいと評価が変化し、8月の物価は実際に下落に転じました。企業向けサービス価格も上昇テンポが鈍化しており、価格の停滞感が強まっています。これは企業の収益構造や価格戦略に影響を与える可能性があり、今後の物価動向には注意が必要です。
総じて、令和7年9月の報告では、個人消費と設備投資において回復の兆しが見られる一方、企業収益や物価の面では慎重な見方が必要です。先行きについては、雇用・所得環境の改善や政策効果による回復が期待されるものの、通商政策や物価上昇、金融市場の変動など、複数のリスク要因に引き続き留意する必要があります。今後も月例経済報告を通じて、経済の微細な変化を丁寧に読み解いていくことが重要です。
10月の月例経済報告が公表されましたら、再度、解説致します。
