借地権の承諾料の相場と更地価格との関係-損しないための基礎知識-
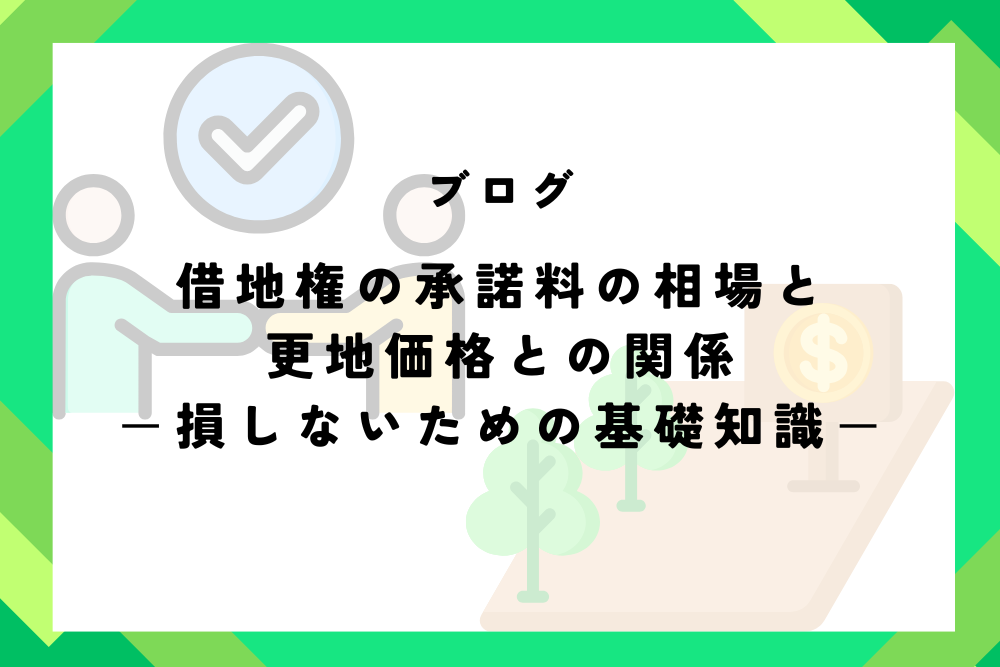
1.はじめに
借地人、地主にとって、「各種承諾料」がどのように求められるのかは、非常に関心のあることだと思われます。
各種承諾料と述べましたが、借地権者が以下のことを行う際には、地主の承諾が必要となり、その承諾の対価として、承諾料を支払うことになります。
- 譲渡承諾料:借地権の譲渡に際して必要となる。
- 建替承諾料:建物の建替に際して必要となる。
- 条件変更承諾料:単なる建替ではなく、非堅固から堅固、用途変更が生じる場合に必要となる。
後に説明しますが、上記に関連して必要となる承諾料のうち、建替承諾料と条件変更承諾料は「更地価格」に対する割合として、把握されることが通常です。(譲渡承諾料は借地権価格に対する割合となります。)
では、この「更地価格」はどのように決まるのでしょうか。
実は、これは簡単なようで、そうでもないのです。
「更地価格」と言ってしまうと、単なる土地の価格ということになりますが、土地の価格といっても、固定資産税評価額による価格、路線価による価格、地価公示価格による価格、実勢価格と4つの価格があります。

以上のとおり、借地権は、建物の建替えや契約の更新、名義の変更(譲渡)など、さまざまな場面で「承諾料」の支払いが発生します。しかし、これらの承諾料がどのように決まり、どの程度が「相場」なのか、また、その基準となる「更地価格」はどのように算定されるのか、実際にはよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、借地権に関わる各種承諾料のうち、更地価格が基礎となる条件変更承諾料・建替承諾料の相場や計算方法、そしてその基準となる更地価格の決め方について、実務経験や判例、専門家の知見をもとに分かりやすく解説します。地主・借地人の双方にとって「損をしない」ためのポイントや、トラブルを未然に防ぐための注意点も網羅していますので、これから借地権の取引や交渉を控えている方、または既に借地権をお持ちの方にも役立つ内容となっています。
この記事をよんでわかること
- 建替・条件変更承諾料の意味
- 承諾料の相場と算定方法
- 更地価格の定義と評価指標
- 更地価格の決め方と実務例
- 借地非訟手続きの概要
- 損をしないための交渉ポイント
2.建替承諾料と条件変更承諾料の基礎知識
借地権とは、土地の所有者(地主)から一定期間、土地を借りて利用する権利を指します。借地権者(借地人)は、土地を借りてその上に建物を所有し、居住や事業などに利用することができます。借地権は、民法や借地借家法などの法律に基づいて成立し、地主と借地人の間で契約が結ばれます。
借地権の契約期間中、借地人が土地の利用方法を変更したり、建物を建て替えたりする場合には、地主の承諾が必要となります。この際、地主が承諾することの対価として「承諾料」が発生します。この承諾料には、建替承諾料と条件変更承諾料の2つがあります。

(1)建替承諾料
借地人が既存の建物を取り壊し、新たに建物を建て替える場合に必要となる承諾料です。建物の老朽化やライフスタイルの変化により、建替えを希望するケースは多く見られますが、建替えによって土地の利用価値が変わることから、地主の承諾とその対価が求められます。
(2)条件変更承諾料
単なる建替えではなく、建物の構造を非堅固(木造など)から堅固(鉄筋コンクリート造など)に変更する場合や、建物の用途を住宅から店舗・事務所などに変更する場合に必要となる承諾料です。これらの変更は、土地の価値や利用状況に大きな影響を与えるため、地主の承諾が不可欠となります。
これらの承諾料は、地主と借地人の間で協議して決定されますが、実務上は「更地価格」を基準とした一定の割合で算定されることが一般的です。次章では、各種承諾料の相場や算定基準について詳しく解説します。
3.承諾料の相場と算定基準
借地権における建替承諾料や条件変更承諾料は、地主と借地人の協議によって決定されますが、実務上は「更地価格」を基準とした一定の割合で算定されることが一般的です。ここでは、各種承諾料の相場や算定基準について解説します。

(1)建替承諾料
まず、建替承諾料については、更地価格の3~5%程度が目安とされています。これは、建物の建替えによって土地の利用価値が変化し、地主にとっても一定の利益やリスクが生じるため、その対価として支払われるものです。例えば、更地価格が1億円の場合、建替承諾料はおおよそ300万円から500万円程度となります。
(2)条件変更承諾料
次に、条件変更承諾料は、更地価格の10%程度が相場とされています。これは、建物の構造を非堅固から堅固に変更したり、用途を住宅から店舗や事務所に変更したりする場合に発生します。こうした条件変更は、土地の価値や利用状況に大きな影響を与えるため、承諾料も高めに設定される傾向があります。
なお、これらの割合はあくまで一般的な目安であり、実際には地域の慣行や土地の個別事情、地主・借地人間の交渉力、過去の判例などによって変動します。また、承諾料の算定にあたっては、不動産鑑定士による評価を活用することもあります。
このように、承諾料の相場や算定基準は一律ではなく、さまざまな要素を考慮して決定されます。次章では、承諾料の基準となる「更地価格」とは何か、その定義や役割について詳しく解説します。
4.更地価格とは何か
更地価格とは、建物などの工作物が何も建っていない「更地」として、その土地が自由に利用できる状態で売買される場合の市場価値を指します。つまり、土地そのものの純粋な価値を示すものであり、建物や借地権などの権利が付着していない状態での価格です。
借地権においては、建替承諾料や条件変更承諾料などの算定基準として「更地価格」が用いられるのが一般的です。これは、土地の本来の価値を基準にすることで、地主・借地人双方にとって公平な金額を算出しやすくするためです。たとえば、建物の建替えや用途変更によって土地の利用価値が大きく変わる場合、その変化に見合った承諾料を設定する必要がありますが、その際の基準となるのが更地価格です。
更地価格は、借地権価格や建物価格とは異なります。借地権価格は、借地権という権利そのものの価値(=更地価格×借地権割合)であり、建物価格は建物自体の価値です。承諾料の算定においては、これらを混同しないことが重要です。
また、更地価格は一律に決まるものではなく、土地の立地や形状、周辺環境、法的規制などさまざまな要素によって変動します。次章では、この更地価格が実際にどのように決められるのか、評価方法や算定手順について詳しく解説します。

5.更地価格の決め方
更地価格は、借地権における承諾料の算定基準として非常に重要ですが、その評価方法にはいくつかのアプローチがあります。実務では、主に次の4つの指標が参考にされます。

(1)固定資産税評価額
自治体が毎年算定し、納税通知書などで確認できる価格です。
不動産を所有されている方には、毎年納税通知書が送られきますので、身近に思われる方も多いかもしれません。
後に詳しく説明しますが、地価公示価格の70%となるように設定されています。
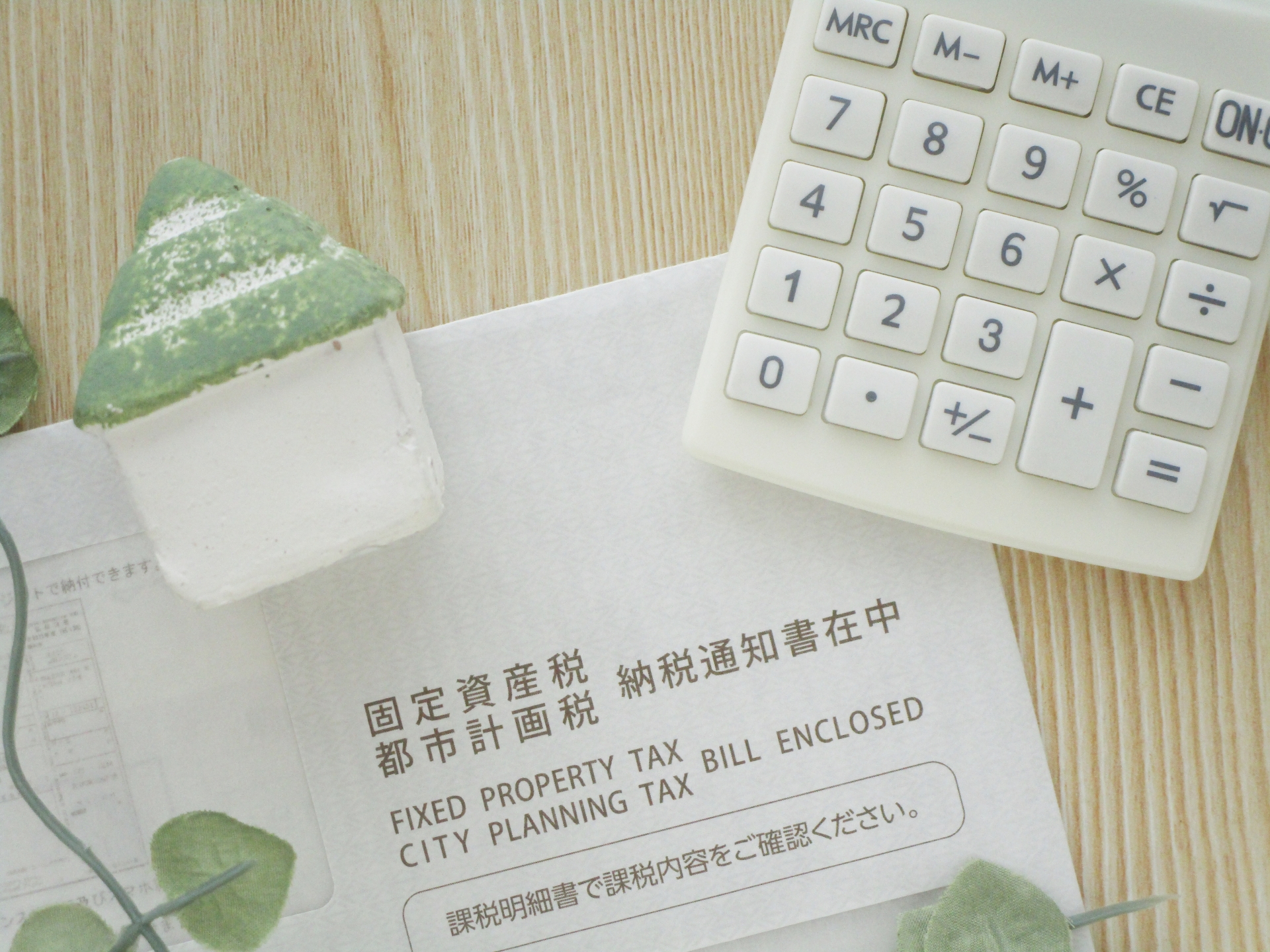
(2)路線価
国税庁が毎年公表する、各路線(道路)ごとに設定された1㎡あたりの土地価格です。
毎年、7月頃に公表されます。
正確には、相続税路線価といい、相続税や贈与税の計算に使われるものです。
路線価は、地価公示価格の80%を目安とされています。
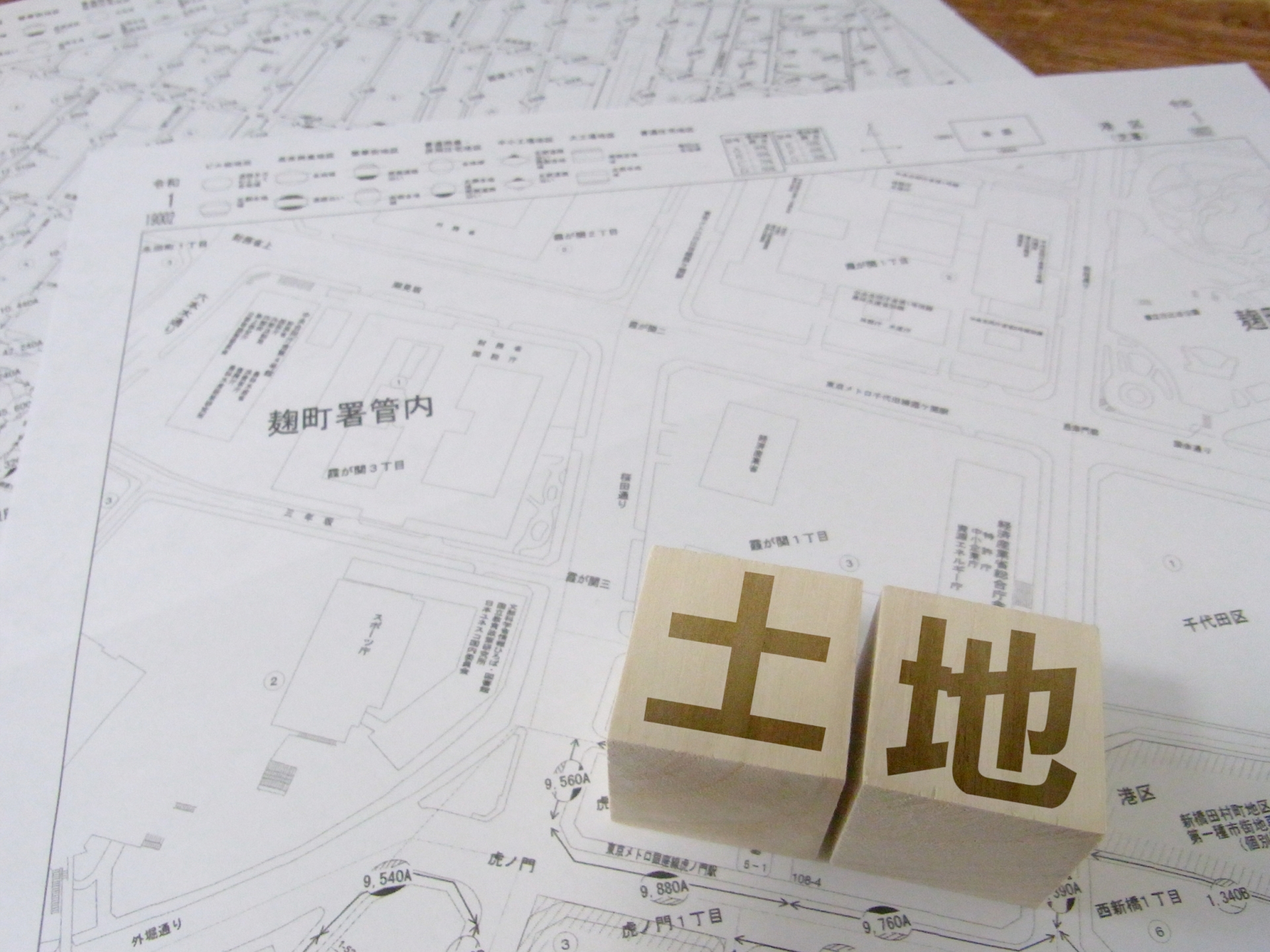
(3)地価公示価格
国土交通省が毎年発表する、標準地ごとの1㎡あたりの価格です。一般の土地取引の指標等となることを目的としています。近隣の標準地の価格を参考にすることで、より客観的な更地価格の把握が可能です。
(4)実勢価格
実際に近隣で取引された土地の売買価格です。相場、と言えば分かりやすいでしょうか。
先の3つの価格と比較しますと、これが実勢価格です、というように公表はされていませんので、正確な実勢価格の把握は困難かもしれません。
実勢価格を知るだけでしたら、地場の不動産業者にヒアリングすることで、おおまかな水準は知ることは可能でしょう。
性格な実勢価格を知るとともに、その価格の妥当性を証明する必要がありましたら、不動産鑑定士による鑑定評価を依頼することになります。
6.基準となる更地価格は何なのか
ここまでで、建替承諾料と条件変更承諾料について解説し、その基準となる更地価格についても説明させていただきました。
では、基準となる更地価格はどのように決まるのかについて、以下説明していきます。
ここからは非常に重要で、本ブログの核心ともいえる部分となります。

(1)2つのステップ
2つの場合分けといいますか、交渉の段階に応じて、2つのステップに分けて考える必要があります。
2つのステップは何かといいますと、
- 地主・借地人間での話し合いの段階
- 借地非訟
上記の2つの段階となります。以下、それぞれ説明していきます。
(2)話し合いの段階
話し合いの段階で話しがまとまるのでしたら、結論として、基準となる更地価格をどのように決めようが、更には、更地価格に対する割合もどのように決めようが、当事者の自由です。
極論すれば、理論的に更地価格や更地価格に対する割合をいくらにするか、などと決めずに、金額ベースでざっくりいくら、ということでも構いません。
当事者同士が合意できれば、それで問題ありません。
ここは非常に重要です。
更地価格に対する割合などは、そのようにされていることが多い、というだけで、法律などで決まっている訳ではありません。
また、その割合も後に説明する借地非訟の手続の中で決まったものを準用しているに過ぎません
ですが、地主と借地人がよほど親密な関係でない限り、話し合いというよりは交渉に近いやり取りになると思われますので、ある程度、論理的なアプローチが必要となるのでしょう。そこで、先のとおり、借地非訟の数値が準用されている、というのが実態です。
では、借地非訟の数値(更地価格に対する割合)が準用されているとして、その更地価格はどうしたらいいのでしょうか。
これも話し合いで決めればいい、ということになりますが、先に4つの更地価格を説明させていただきました。更地価格は、4通りあります。
以下、4つの価格を利用する場合について、説明します。
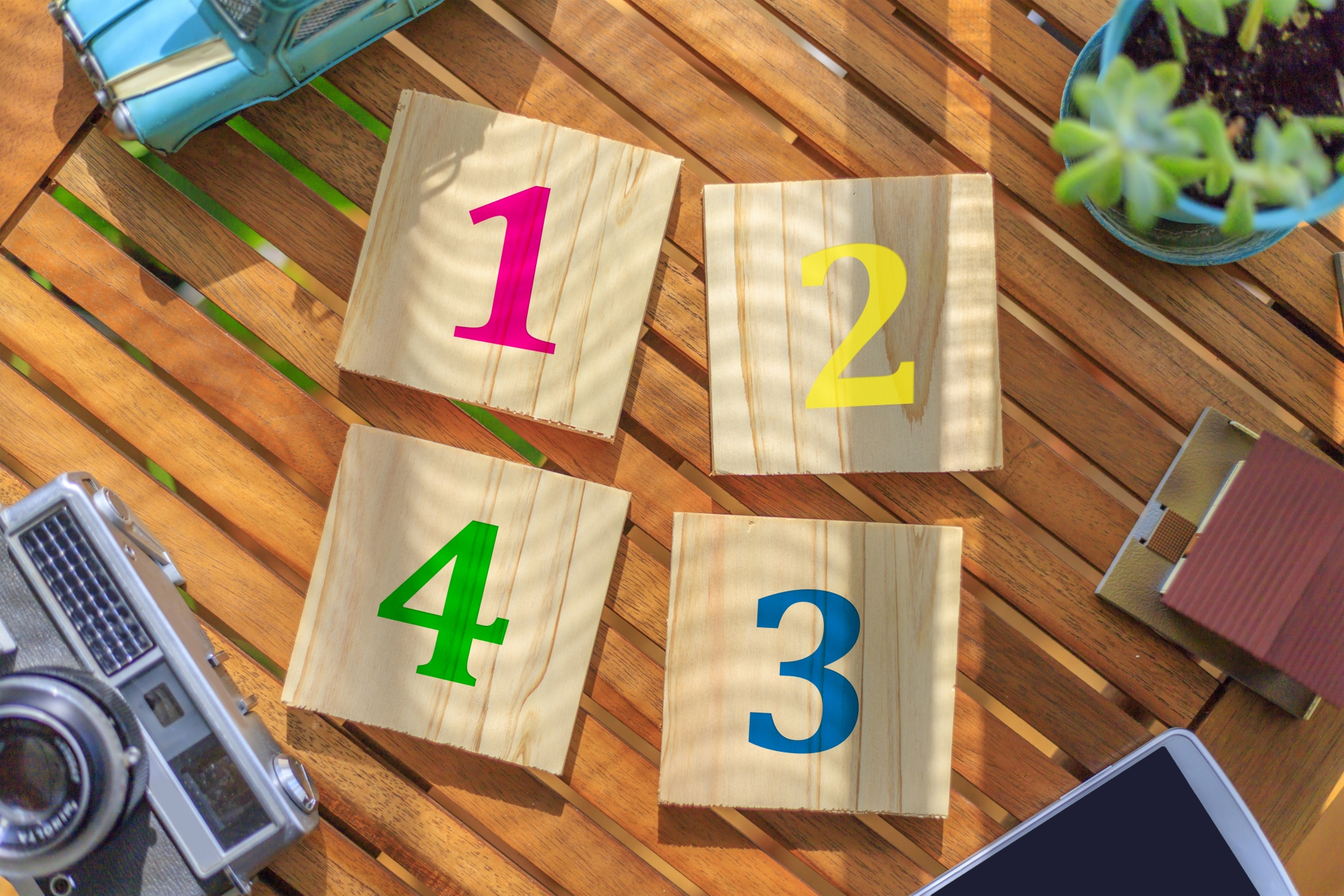
①固定資産税評価額
手間がかからず、分かりやすい、という点では、この固定資産税評価額を利用する方法が優れています。
毎年、5~6月頃に土地の所有者(地主)に、固定資産税の納税通知書が送られきます。そして、この納税通知書に固定資産税の土地の評価額が記載されていますので、これを利用するだけなので、簡単で手間もかかりません。
借地人の方でしたら、借地の契約書をもって、市町村役場(東京23区は都税事務所)に行けば、固定資産税の評価証明書を入手できます。
手間がかからず、分かりやすいという優れものの固定資産税評価額ですが、地主にとってはデメリット、借地人にとってはメリットとなることがあるので、注意が必要です。
それは、固定資産税評価額は、地価公示価格の70%となるように設定されていますので、後に説明する公示価格、路線価(路線価は公示価格の80%)よりも安いということです。
更地価格が安いということは、その更地価格に割合を乗じますので、各種承諾料も安くなる、ということになります。
これには注意をして下さい。
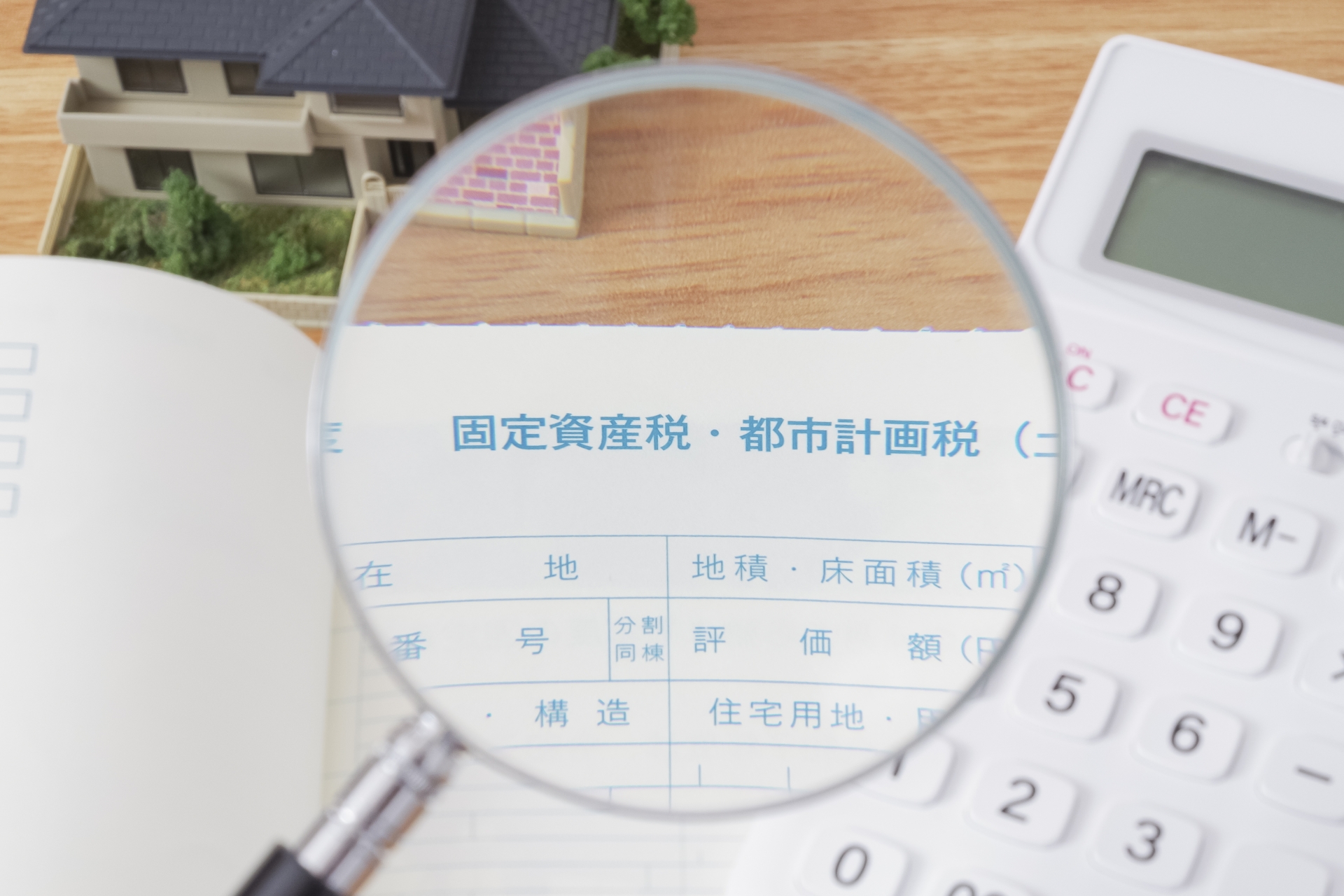
②路線価
こちらも、固定資産税評価額に次いで、手間等がかからないという点で、優れています。
相続税路線価は、国税庁のホームページから閲覧可能です。
対象となる土地の路線価を調べて、その路線価に土地の面積を乗じれば、路線価による評価額となります。(路線価は、1㎡当たりの単価です。)
路線価も利用のしやすさという点では優れものですが、やはり注意点があります。
先の固定資産税評価額でも触れましたが、路線価は公示価格の80%となるように設定されていますので、公示価格よりも安いということです。
また、固定資産税評価額は、土地の個別格差(形状や角地など)を反映させたものとなっていますが、路線価そのものは、標準的な土地の価格になっているということです。
極端な個別格差がなければ、路線価そのものでもいいかもしれませんが、著しい不整形やとても大きな高低差がある場合などは、そのまま路線価を使っていいのか、ということは悩みどころとなります。
なお、路線価にも、固定資産税評価額と同様、個別格差を反映させることは出来ますが、これは自身で計算しなければならず、手間がかかります。
これはデメリットです。
③公示価格
公示価格は、土地取引の指標となるのが目的ですので、先の2つと比較すると、この公示価格が望ましいのかもしれません。(固定資産税評価額と路線価は課税目的ですので、そもそもの目的が異なります。)
但し、この公示価格そのものを利用するのは、不動産関係者でない限り、難易度が高いと考えます。
公示価格そのものは、国土交通省のHPから確認することが出来ます。公示価格は、先の固定資産税評価額、路線価と異なり、具体の地点が評価されています。調べたい土地が公示価格のすぐ近くにあれば、公示価格を参考にすることも出来ますが、少し離れているような場合には、補正が必要ですので、これはかなり面倒ではないかと考えます。
なお、簡便的な方法にはなりますが、先にも触れたとおり、路線価は公示価格の80%となるように設定されていますので、この関係を利用して、路線価を80%で割り戻せば、公示価格水準となります。
ですので、公示価格とは言っておりますが、この路線価を80%で割り戻した価格を実質的な公示価格とみなして利用するのが活用しやすいのではないかと考えています。

④実勢価格
これを書いている時点(2025年9月)において、主要都市の中心部では、路線価の2~3倍程度が実際の取引価格となっているところもあります。また、私自身は把握できておりませんが、過疎化などが進んでいる地域などでは反対に、先の公示価格などよりも、実際の取引価格が安い地域もあるかもしれません。
このような地域では、実勢価格をもって更地価格としたい、ということもあるかもしれません。
ですが、実勢価格はどのように調べればいいでしょうか。近年では、インターネット等で不動産価格を調べることは容易になりましたし、不動産業者にヒアリングするとうことも考えられます。
実勢価格というのは、公示価格などとは異なり、開示されていませんし、調べた人やヒアリングした不動産業者の判断にしか過ぎません。従いまして、これが実勢価格です、という客観的な証明にはなりません。
では、客観的な実勢価格を知りたい場合には、どうすればいいかと言いますと、不動産鑑定士に不動産鑑定評価をお願いする、ということになります。
専門家にお願いするので、一見安心的な方法に思われるかもしれませんが、不動産鑑定士にお願いする場合には、費用がかかります。
また、鑑定評価は判断ですから、高めに考える鑑定士もいれば、安めに考える鑑定士もいて、仮に、複数の鑑定業者にお願いすれば、幅が生じてくる可能性もあることは、しっておいて下さい。
なお、不動産鑑定士にお願いするメリットとして、更地価格だけでなく、承諾料も合わせて算出してもらえる可能性もある、ということでしょう。(実際に承諾料を算出してもらえるかどうかは分かりませんので、注意して下さい。)

(3)借地非訟
当事者同士の話し合いでまとまらなかった場合には、借地非訟手続きとなります。
借地非訟手続きとは、借地契約に関するトラブルや地主の承諾が得られない場合に、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えるための特別な裁判手続きです。たとえば、借地人が建物の建替えや増改築、借地条件の変更を希望しても、地主が承諾しない場合や、承諾料の金額で折り合わない場合に利用されます。借地非訟手続きは、借地借家法に基づき、借地人が地方裁判所に申し立てることで開始されます。

この手続きの特徴は、通常の訴訟と異なり非公開で進められる点や、不動産鑑定にかかる費用を国が負担する点です。裁判所は、弁護士や不動産鑑定士などで構成される鑑定委員会の意見を参考にしながら、承諾の可否や承諾料の金額を決定します。手続きの途中で和解が成立することも多く、当事者間の話し合いによる解決も促されます。
借地非訟手続きは、地主と借地人の利害が対立しやすい場面で、公平な第三者である裁判所が関与することで、円滑な解決を図るための有効な手段です
借地非訟へと移行しますと、裁判所の鑑定委員が承諾料を算定してくれます。
裁判所が決定してくれますので、便利とも言えます。
但し、通常の裁判よりも簡易的なものとは云え、司法手続きとなりますので、通常は弁護士にお願いすることが必要となり、弁護士費用に合わせて、期間も要しますので、この点には注意が必要です。
先に説明させていただきましたが、更地価格に対する割合は、この借地非訟手続きによるものを参考にしていますので、更地価格に対する割合は、特殊な案件でない限り、一般的な割合で収まるでしょう。
では、更地価格はどうなるでしょうか。先のとおり鑑定委員が鑑定をしますが、私の経験上、実勢価格と公示ベース価格の間ぐらいで決まることが多いように感じています。
もちろん、これも地域や時期などによって異なってくるでしょうから、かならずそうなる訳ではありませんので注意して下さい。
7.まとめ
建替承諾料、条件変更承諾料とその算定の基準となる更地価格について、説明させていただきました。
建替承諾料、条件変更承諾料はともに、更地価格に対する割合として、把握されておりますが、その更地価格が何なのかということに関して、明記されている文献等はあまりないのではないでしょうか。
そのため、建替承諾、条件変更承諾が必要となった時に、慌てて調べても、参考となる資料等が見つからず、困ってしまう方も多いことでしょう。
結局のところ、更地価格といっても、その更地価格をどうするかは、明確に決まってはおらず、当事者同士で合意出来ていればなんでもいいということになります。
合意が出来なければ、借地非訟となりますが、この場合には、公示価格と実勢価格の間ぐらいが更地価格となることが多いです。
このことを知っていれば、相手方から、極端な金額を提示された時に、対処も可能になるものと思わます。
