令和7年7月29日に発表された月例経済報告(令和7年7月)について、解説します。
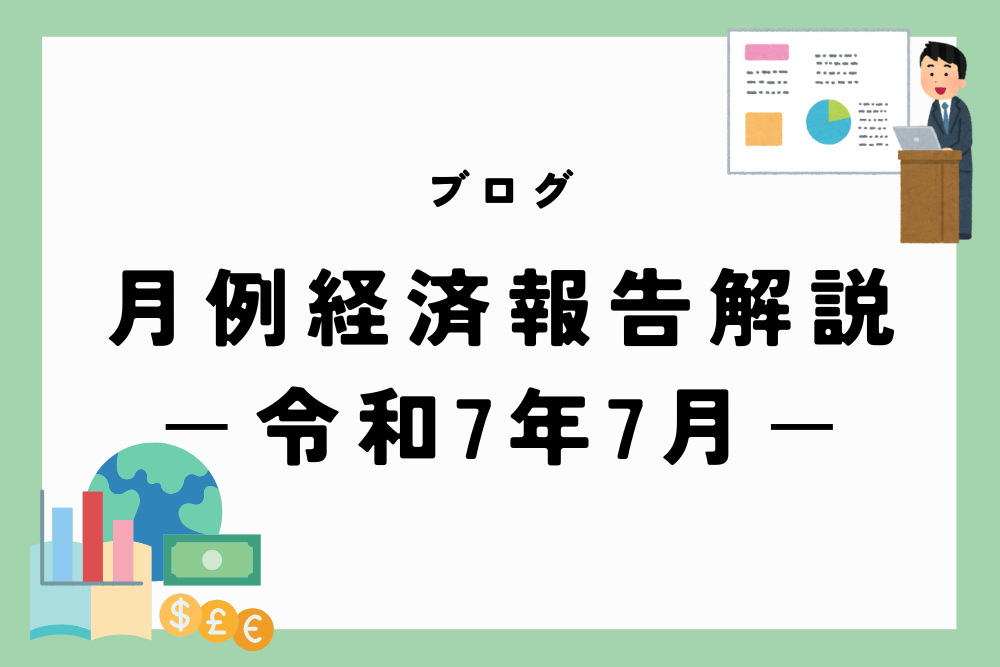
令和7年7月の月例経済報告について、解説します。
月例経済報告については、こちらで説明しておりますので、よければご参照下さい。
懸案でありました通商政策ですが、7月22日に日米両政府は関税政策に関する合意を発表しました。自動車や部品などに課される追加関税は、従来の25%から15%に引き下げられ、相互関税も同様に調整されました 。
これを反映して、7月の月例経済報告は、先月と比較して、変化のある項目が多くなりました。
この記事を読んで分かること
- 景気の基調判断は引き続き「緩やかな回復」とされており、日米通商合意により不透明感がやや緩和された。
- 個人消費は持ち直し傾向を維持しており、消費者マインドも「下げ止まり」の兆しが見られる。
- 輸出は「持ち直し」から「横ばい」へと評価が後退し、米国関税措置の影響が依然として懸念材料となっている。
- 輸入はアジアからの回復が継続しており、内需の底堅さを示す内容となっている。
- 国内企業物価は「上昇テンポの鈍化」が見られ、物価動向への警戒感がやや強まっている。
1.令和7年7月分について
(1)主要な項目
主要な項目を、令和7年6月、令和7年7月について、以下掲載します。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 | |
| 基調判断 | 景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感がみられる | 景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している |
| 個人消費 | 消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる | 消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる |
| 設備投資 | 持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
| 住宅建設 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 公共投資 | 底堅く推移している | 底堅く推移している |
| 輸出 | このところ持ち直しの動きがみられる | おおむね横ばいとなっている |
| 輸入 | このところ持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
| 貿易・サービス収支 | 赤字となっている | 赤字となっている |
| 生産 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている |
| 企業収益 | 改善しているが、通商問題が及ぼす影響等に留意する必要がある | 改善しているが、通商問題が及ぼす影響等に留意する必要がある |
| 業況判断 | このところおおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 倒産件数 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 雇用情勢 | 改善の動きがみられる | 改善の動きがみられる |
| 国内企業物価 | 緩やかに上昇している | このところ上昇テンポが鈍化している |
| 消費者物価 | 上昇している | 上昇している |
以下、記述に変化のありました基調判断、個人消費、輸出、輸入、業況判断、国内企業物価について詳しくみていきます。

(2)基調判断
①令和7年6月と令和7年7月の比較
令和7年(2025年)6月と7月の詳細を、以下記載します。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 景気は、緩やかに回復しているが、米国の通商政策等による不透明感がみられる。 米国の関税措置について、政府を挙げて対応することを始め、経済財政運営に万全を期す。 デフレ脱却を確かなものとするため、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、4月25 日に取りまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」の施策を実施する。 また、「経済財政運営と改革の基本方針2025(仮称)」等を取りまとめる。 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 | 景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。 米国の関税措置について、今般の日米間の合意を踏まえ、引き続き必要な対応を行いながら、経済財政運営に万全を期す。 「経済財政運営と改革の基本方針2025~『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ~」に基づいて、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。 このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、4月25 日に取りまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」の施策を実施する。 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 |
②解説
令和7年6月と7月の基調判断では、いずれも「景気は緩やかに回復している」との表現が用いられており、日本経済が持ち直しの局面にあるという認識に変化はありません。これは、個人消費や設備投資の回復、雇用環境の改善などを背景に、景気が底堅く推移していることを示しています。
ただし、両月の基調判断には微妙な違いが見られます。6月の報告では「米国の通商政策等による不透明感がみられる」とされており、米国関税措置など外的要因による先行き不安が強調されていました。一方、7月の報告では「米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの」と表現が変化しており、やや前向きなトーンに転じています。
この違いは、7月の報告に「今般の日米間の合意を踏まえ」という文言が加えられていることからも明らかです。つまり、6月時点では不透明だった米国との通商関係に一定の進展があり、経済への影響が限定的であるとの見方が強まったことが背景にあります。
両月とも、景気回復の基調は維持されているものの、外的リスクの捉え方に変化が生じている点が重要です。6月は警戒感が強く、政府の対応に重点が置かれていたのに対し、7月は合意を踏まえた対応が進んでいることが示され、先行きに対する不安がやや緩和された印象を受けます。 このように、7月の基調判断は、景気の回復傾向を維持しつつも、米国関税措置など外的要因への対応状況に応じて表現が変化していることが分かります。

(3)個人消費
①令和7年6月と令和7年7月の比較
令和7年(2025年)6月と7月の詳細になります。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 個人消費は、消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 「四半期別GDP速報」(2025 年1-3月期2次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比0.1%増となった。 また、「消費動向指数(CTI)」(4月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比0.0%減となった。 個別の指標について、需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(4月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、総世帯)の実質値は前月比0.5%減となった。 供給側の統計をみると、「商業動態統計」(4月)では、小売業販売額は前月比0.5%増となった。 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。 また、消費者マインドは、このところ弱含んでいる。 さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直している。 家電販売は、持ち直している。 旅行は、おおむね横ばいとなっている。 外食は、緩やかに増加している。 こうしたことを踏まえると、個人消費は、消費者マインドが弱含んでいるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。 | 個人消費は、消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 「四半期別GDP速報」( 2025 年1-3月期2次速報)では、民間最終消費支出の実質値は前期比0.1%増となった。 また、「消費動向指数(CTI)」(5月)では、総消費動向指数(CTIマクロ)の実質値は前月比0.1%増となった。 個別の指標について、需要側の統計をみると、「消費動向指数(CTI)」(5月)では、世帯消費動向指数(CTIミクロ、総世帯)の実質値は前月比1.8%増となった。 供給側の統計をみると、「商業動態統計」(5月)では、小売業販売額は前月比0.6%減となった。 消費動向の背景をみると、実質総雇用者所得は、緩やかに持ち直している。 また、消費者マインドは、下げ止まっている。 さらに、足下の状況について、ヒアリング結果等を踏まえると、新車販売台数は、持ち直している。 家電販売は、持ち直している。 旅行は、おおむね横ばいとなっている。 外食は、緩やかに増加している。 こうしたことを踏まえると、個人消費は、消費者マインドの改善に遅れがみられるものの、雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる。 先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される。ただし、消費者マインドの動向に留意する必要がある。 |
②解説
両月の記述を比較すると、全体としては「持ち直しの動きがみられる」との評価で一致しているものの、消費者マインドや統計データの変化に応じて、表現やニュアンスに違いが見られます。
まず、共通点として挙げられるのは、個人消費の全体的な評価です。6月・7月ともに、「雇用・所得環境の改善の動きが続く中で、持ち直しの動きがみられる」とされており、労働市場の安定が消費を下支えしているという認識に変化はありません。また、ヒアリング結果に基づく実態把握でも、新車販売や家電販売が「持ち直している」、外食が「緩やかに増加している」、旅行が「おおむね横ばい」とされており、消費行動の傾向にも大きな違いは見られません。
一方で、相違点として注目すべきは、「消費者マインド」に関する評価の変化です。6月の報告では「消費者マインドが弱含んでいる」とされていたのに対し、7月の報告では「消費者マインドの改善に遅れがみられる」と表現が変化しています。さらに、「消費者マインドは、このところ弱含んでいる」(6月)から「消費者マインドは、下げ止まっている」(7月)へと、やや前向きなトーンに転じている点も見逃せません。これは、消費者心理が底を打ちつつある兆しを示しており、今後の消費回復に対する期待感が高まりつつあることを示唆しています。
また、統計データの動向にも違いが見られます。6月の報告では、「消費動向指数(CTI)」のマクロ指標が前月比0.0%減、ミクロ指標が0.5%減と、やや弱含みの結果でした。一方、7月の報告では、マクロ指標が0.1%増、ミクロ指標が1.8%増と、明確な改善が確認されています。これは、実際の消費行動が回復基調にあることを裏付けるものであり、基調判断の安定性を支える要因となっています。
ただし、供給側の統計である「商業動態統計」においては、6月(4月分)の小売業販売額が前月比0.5%増だったのに対し、7月(5月分)は0.6%減とやや弱含みの結果となっており、全体としてはまだ力強さに欠ける面も残されています。
このように、 7月における個人消費は、6月から7月にかけて「持ち直しの動きがみられる」という評価を維持しつつも、消費者マインドの変化や統計データの改善を反映して、やや前向きなトーンへと変化しています。特に、「消費者マインドの下げ止まり」や「CTIの改善」は、今後の景気回復を占ううえで重要なシグナルといえるでしょう。 先行きについては、両月ともに「雇用・所得環境が改善する下で、持ち直していくことが期待される」との見通しが示されており、引き続き消費者心理の動向に注視する必要があります。

(3)輸出
①令和7年6月と令和7年7月の比較
令和7年(2025年)6月と7月の詳細です。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。 地域別にみると、アジア向けの輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる。 米国向けの輸出は、輸送用機器を中心に、このところ持ち直しの動きがみられる。 EU及びその他地域向けの輸出は、おおむね横ばいとなっている。 先行きについては、米国の関税引上げによる直接的な影響、通商問題による世界経済を通じた間接的な影響等に留意する必要がある。 | 輸出は、おおむね横ばいとなっている。 地域別にみると、アジア、米国、EU及びその他地域向けの輸出は、おおむね横ばいとなっている。 先行きについては、米国の関税引上げによる直接的な影響、通商問題による世界経済を通じた間接的な影響等に留意する必要がある。 |
②解説
令和7年6月と7月の比較をすると、景気の外需面における変化が浮き彫りになります。6月の報告では「輸出は、このところ持ち直しの動きがみられる」とされていたのに対し、7月の報告では「輸出は、おおむね横ばいとなっている」と表現が変化しており、輸出の勢いにやや陰りが見られることが分かります。
地域別の動向を見ても、6月はアジアおよび米国向け輸出について「持ち直しの動きがみられる」と前向きな評価がなされていました。特に米国向けは「輸送用機器を中心に」と具体的な品目にも言及されており、輸出の回復が一部で顕著だったことがうかがえます。一方、7月の報告では、アジア、米国、EUおよびその他地域すべてにおいて「おおむね横ばい」とされており、地域を問わず輸出の伸びが鈍化している様子が読み取れます。
この変化の背景には、米国関税措置の影響があると考えられます。両月ともに先行きのリスクとして「米国の関税引上げによる直接的な影響」や「通商問題による世界経済を通じた間接的な影響」に留意する必要があると明記されており、外需の不確実性が依然として高い状況にあることが示されています。 つまり、6月から7月にかけて「持ち直し」から「横ばい」へとトーンがやや後退しており、外需の回復に一服感が出ていることが分かります。今後の輸出動向を見極めるうえでは、米国との通商交渉の行方や世界経済の動向が引き続き重要な要素となるでしょう。
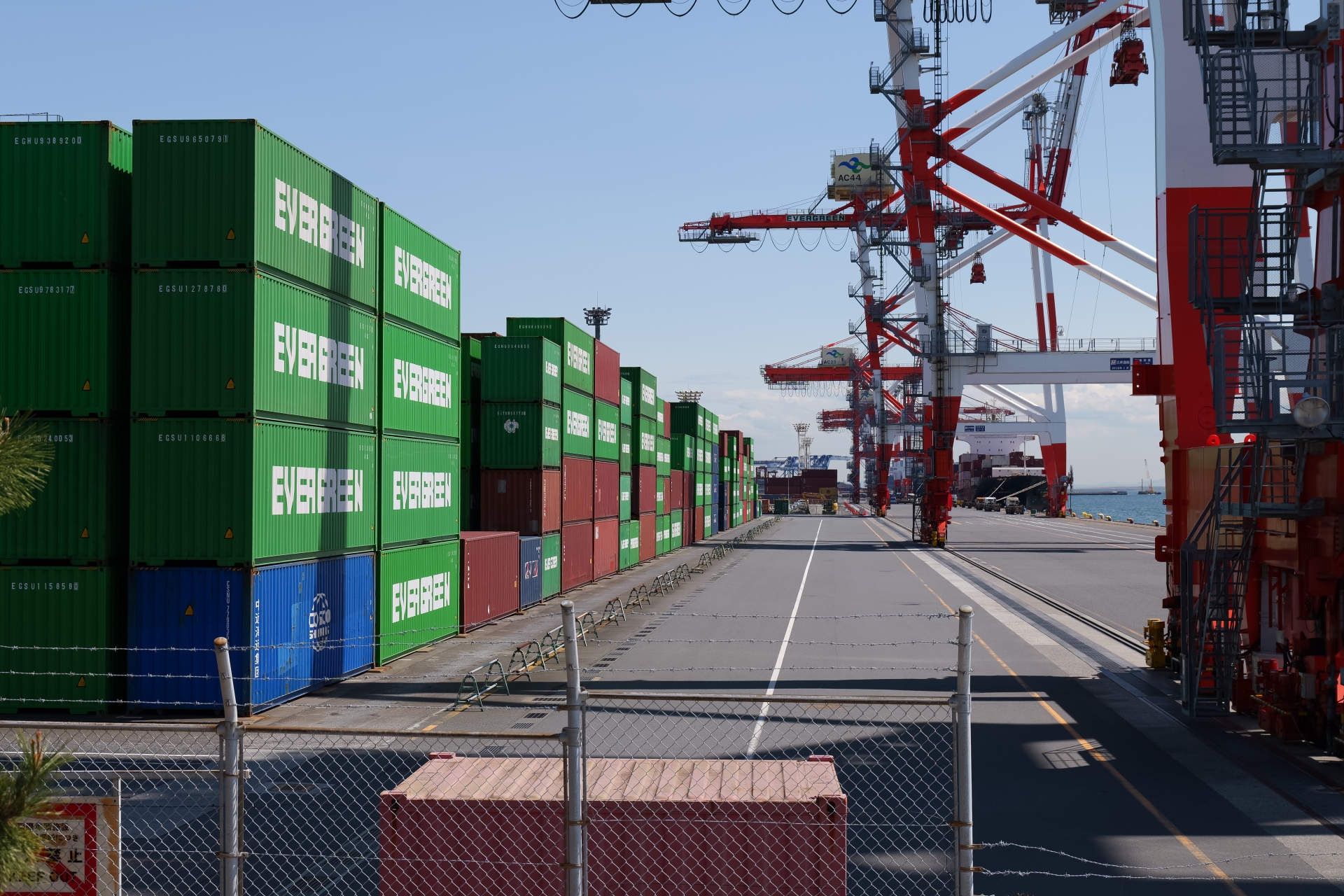
(3)輸入
①令和7年6月と令和7年7月の比較
令和7年(2025年)6月と7月の詳細を掲載します。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 輸入は、このところ持ち直しの動きがみられる。 地域別にみると、アジアからの輸入は、このところ持ち直しの動きがみられる。 米国及びEUからの輸入は、おおむね横ばいとなっている。 先行きについては、持ち直しに向かうことが期待される。 | 輸入は、持ち直しの動きがみられる。 地域別にみると、アジアからの輸入は、持ち直しの動きがみられる。 米国及びEUからの輸入は、おおむね横ばいとなっている。 先行きについては、持ち直しに向かうことが期待される。 |
②解説
令和7年6月と7月では、いずれも「持ち直しの動きがみられる」と評価されており、内需の回復傾向が継続していることが示されています。特に、アジアからの輸入については、両月ともに「持ち直しの動きがみられる」と明記されており、地域別の動向においても一致した見解が示されています。
一方、米国およびEUからの輸入については、6月・7月ともに「おおむね横ばい」とされており、これらの地域からの輸入には大きな変化が見られていないことが分かります。つまり、輸入の地域別評価は、6月と7月でほぼ同様の内容となっており、基調判断に大きな差異はないと言えます。
ただし、細かな表現の違いに注目すると、6月の報告では「このところ持ち直しの動きがみられる」とやや慎重な表現が用いられているのに対し、7月では「持ち直しの動きがみられる」と、より明確な回復の兆しを示す表現に変化しています。この違いは、輸入の回復傾向が一段と定着しつつあることを示唆している可能性があります。
また、先行きの見通しについては、両月ともに「持ち直しに向かうことが期待される」とされており、今後の輸入動向に対して前向きな期待が示されています。これは、国内の生産活動や消費の回復に伴い、輸入需要が増加する可能性を反映したものと考えられます。 総じて、令和7年6月と7月の輸入に関する基調判断は、内容・方向性ともに安定しており、特にアジアからの輸入の回復が継続している点が強調されています。今後も、地域別の輸入動向や国内需要の変化に注目しながら、月例経済報告の基調判断を丁寧に読み解くことが重要です。

(4)業況判断
①令和7年6月と令和7年7月の比較
まず、令和7年(2025年)6月と7月の詳細です。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 企業の業況判断は、このところおおむね横ばいとなっている。 「日銀短観」(3月調査)によると、「最近」の業況判断DIは、「全規模全産業」で前期差0と横ばいだった。 業種別にみると、「全規模製造業」は前期差-1と低下、「全規模非製造業」は前期差+1と上昇した。 6月時点の業況を示す「先行き」は、「最近」 に比べやや慎重な見方となっている。 また、「景気ウォッチャー調査」(5月調査)の企業動向関連DⅠによると、現状判断は低下、先行判断は上昇した。 | 企業の業況判断は、おおむね横ばいとなっている。 「日銀短観」(6月調査)によると、「最近」の業況判断DIは、「全規模全産業」で前期差0と横ばいだった。 業種別にみると、「全規模製造業」は前期差0と横ばい、「全規模非製造業」は前期差0と横ばいだった。 9月時点の業況を示す「先行き」は、「最近」に比べやや慎重な見方となっている。 また、「景気ウォッチャー調査」(6月調査)の企業動向関連DⅠによると、現状判断は上昇、先行判断は低下した。 |
②解説
令和7年6月と7月の業況判断は、いずれも「おおむね横ばい」との表現が用いられており、企業の景況感に大きな変化は見られません。これは、景気の持ち直しが続く中で、企業活動が安定的に推移していることを示しています。
両月の報告では、「日銀短観」の結果が業況判断の根拠として示されています。6月は3月調査、7月は6月調査の結果が引用されており、いずれも「全規模全産業」で業況判断DIが前期差0と横ばいでした。ただし、業種別の動向には違いが見られます。6月の報告では、「製造業」が前期差-1と低下、「非製造業」が+1と上昇しており、業種間でばらつきがありました。一方、7月の報告では、製造業・非製造業ともに前期差0と横ばいで、業種間の差が縮小しています。
また、「景気ウォッチャー調査」による企業動向関連DIの結果にも違いがあります。6月の報告(5月調査)では、現状判断が低下、先行判断が上昇とされており、足元の景況感は弱含みながらも、先行きに対しては前向きな見方が示されていました。これに対し、7月の報告(6月調査)では、現状判断が上昇、先行判断が低下と逆の動きとなっており、企業の景況感が短期的には改善したものの、先行きに対して慎重な姿勢が強まっていることがうかがえます。
両月とも、「先行きは『最近』に比べやや慎重な見方となっている」との記述が共通しており、企業が将来の経済環境に対して不確実性を感じている点は変わりません。これは、米国の通商政策や国内外の物価動向など、外部環境の影響を受けやすい状況が続いていることを反映しています。 総じて、7月の月例経済報告における業況判断は、安定的な企業活動を示しつつも、業種別の動向や先行きの見方に変化が見られます。今後も「日銀短観」や「景気ウォッチャー調査」の結果を通じて、企業の景況感の微細な変化を丁寧に読み解くことが求められます。

(5)国内企業物価
①令和7年6月と令和7年7月の比較
令和7年(2025年)6月と7月の詳細になります。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 国内企業物価は、緩やかに上昇している。 4月の国内企業物価は、前月比0.2%上昇した。 輸入物価(円ベース)は、このところ下落している。 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。 | 国内企業物価は、このところ上昇テンポが鈍化している。 6月の国内企業物価は、前月比0.2%下落した。 輸入物価(円ベース)は、このところ下落している。 企業向けサービス価格の基調を「国際運輸を除くベース」でみると、緩やかに上昇している。 |
②解説
両月を比較すると、物価の動きに対する評価が微妙に変化していることが分かります。
まず、6月の報告では「国内企業物価は、緩やかに上昇している」とされており、価格上昇の継続が確認されていました。実際、4月の国内企業物価は前月比0.2%の上昇となっており、企業間取引価格が緩やかに上昇している状況が反映されています。
一方、7月の報告では「このところ上昇テンポが鈍化している」との表現に変化しており、価格上昇の勢いが弱まっていることが示唆されています。6月の国内企業物価は前月比0.2%の下落となっており、物価の動きが反転したことが基調判断の変更につながっています。
共通点としては、輸入物価(円ベース)がこのところ下落しているという点が両月ともに記載されており、国際的な原材料価格や為替の影響が国内企業物価に波及していることがうかがえます。輸入物価の下落は、企業の仕入れコストの低下につながり、国内物価の抑制要因となる可能性があります。
また、「企業向けサービス価格の基調を『国際運輸を除くベース』でみると、緩やかに上昇している」との記述も両月で一致しており、サービス分野では引き続き価格上昇の動きが続いていることが確認できます。これは、人件費や運営コストの上昇が背景にあると考えられ、物価全体の動向を読み解くうえで重要な要素です。 総じて、国内企業物価は、6月から7月にかけて「緩やかな上昇」から「上昇テンポの鈍化」へと変化しており、物価の動きに対する警戒感がやや強まっています。今後も、輸入物価やサービス価格の動向を注視しながら、企業物価の変化が景気や企業収益に与える影響を丁寧に分析することが求められます。

2.先行きについて
先行きについては、以下のとおりです。
| 令和7年6月 | 令和7年7月 |
| 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクが高まっている。 加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。 また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある。 | 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。 加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。 また、金融資本市場の変動等の影響に一層注意する必要がある。 |
6月、7月ともにほぼ同様ですが、先の基調判断で触れたとおり、通商政策が合意に至りましたので、その合意を反映した書き振りの変化となっています。
3.まとめ
令和7年6月・7月の月例経済報告では、いずれも「景気は緩やかに回復している」との基調判断が示され、日本経済が持ち直しの局面にあるという認識が維持されました。個人消費は、雇用・所得環境の改善を背景に「持ち直しの動きがみられる」とされ、消費者マインドも7月には「下げ止まり」との評価に変化するなど、回復への兆しが見られます。
一方、外需面では変化がありました。輸出は6月に「持ち直しの動き」とされていたものの、7月には「おおむね横ばい」と評価が後退。米国関税措置の影響が引き続き懸念されており、通商政策の不透明感が輸出の勢いを抑える要因となっています。輸入については、アジアからの回復が継続しており、内需の底堅さを示す内容となっています。
企業の業況判断は両月とも「おおむね横ばい」とされ、日銀短観や景気ウォッチャー調査の結果からも、企業活動が安定的に推移していることが確認されました。国内企業物価については、6月は「緩やかに上昇」、7月は「上昇テンポが鈍化」と評価が変化し、物価動向への警戒感がやや強まっています。
加えて、7月には日米間で通商に関する一定の合意が得られたことが報告され、6月時点で強調されていた「不透明感」が「一部に影響がみられるものの」と表現が変化しました。これは、米国関税措置に対する政府の対応が進展し、景気の下振れリスクがやや緩和されたことを示しています。
また、7月29日に開催された月例経済報告等に関する関係閣僚会議では、物価上昇の継続が個人消費に与える影響や、金融資本市場の変動リスクにも言及され、今後の政策運営においても引き続き慎重な対応が求められることが確認されました 。
8月の月例経済報告が公表されましたら、再度、解説致します。

