鑑定評価書、調査報告書、意見書の違いについて解説 -活用場面など分かりやすく説明します。-
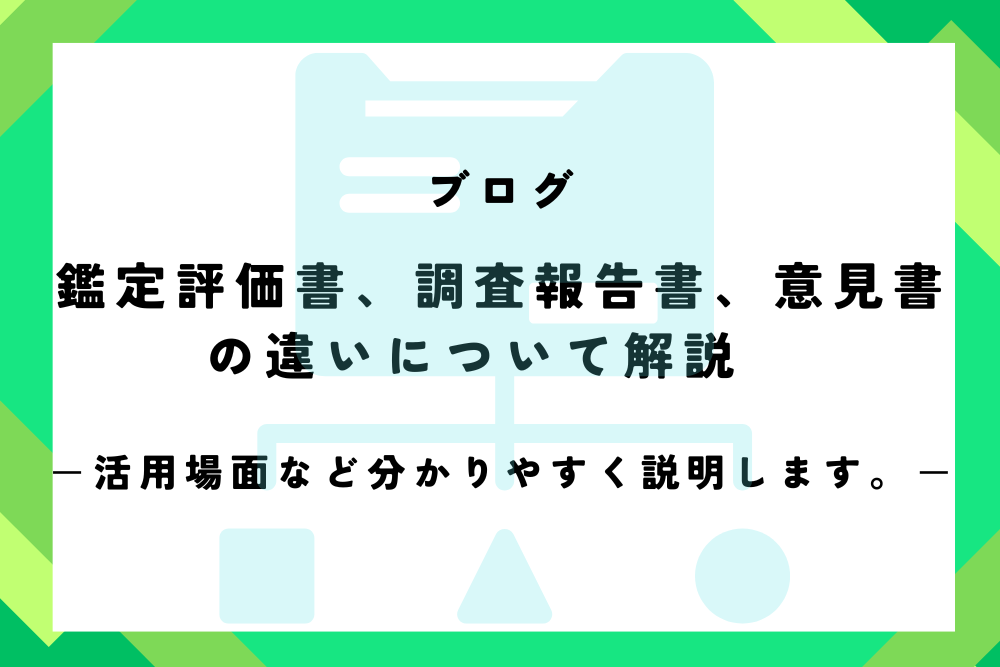
鑑定評価書、調査報告書、意見書について、耳にされたことはありますでしょうか。
なお、ここでの評価書、報告書等は、不動産の価格に関するレポートのことです。
3種類もあると、どれがどう違うのか、分かりにくいですね。
不動産の価格を知りたい時、また、不動産鑑定士による不動産の価格に関するレポートが必要になった時、どれをお願いすればいいのか、頭を悩ませる問題でしょう。
そこで、本部ブログでは、鑑定評価書、調査報告書、意見書について、それぞれの違いと、必要となる場面、あるいは、活用できる場面について、解説します。
この後、説明していきますが、鑑定会社によって、取り扱いが異なるところもありますので、弊社での取り扱いを前提として、説明させていただきます。
1.鑑定評価書、調査報告、意見書の違い
(1)鑑定評価書
不動産鑑定士が鑑定評価を行うにあたり準拠しなければいけないものに、「不動産鑑定評価基準」があります。
この「不動産鑑定評価基準」に完全に則っているものを、「鑑定評価書」といいます。
正式な鑑定評価書、などと言ったりすることもあります。
ですので、「不動産鑑定評価基準」に則っていないものは、「鑑定評価書」とは言えず、後に説明する「調査報告書」、あるいは「意見書」ということになります。
正式な鑑定評価書と、先に触れましたが、「調査報告書」、「意見書」は「不動産鑑定評価基準」に完全には、準拠していませんので、正式な鑑定評価書ではなく、簡易的なものとイメージしてもらえればいいと思います。
鑑定評価が必要となった時、この「鑑定評価書」をお願いしていれば、問題はありません。正式なものなのですから、当たり前ですね。
「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」は、「鑑定評価書」という名称で発行されるものです。
ですので、「鑑定評価書」という名称であれば(当然のことですが、不動産鑑定評価基準に則っている必要があります)、依頼目的を問わず、どのような目的で使用するのであっても問題が生じることはないでしょう。

(2)調査報告書
次に、「調査報告書」です。
先の「鑑定評価書」の説明でも少し触れさせていただいておりますが、「鑑定評価基準」に則っていないものが、「調査報告書」となります。
同じく、則っていないものに「意見書」がありますが、「意見書」の項目で詳しく解説します。
では、「鑑定評価基準」に則るとは、どういうことでしょうか。
ここでは、2つ例を挙げます。
①手法の一部のみを適用する
「不動産鑑定評価基準」によると、3手法を適用することとなっています。
ですので、3手法のうち、一部の手法しか適用しなければ、「不動産鑑定評価基準」に則っていないことになります。
例えば、更地の評価でしたら、通常、取引事例比較法と収益還元法の2手法を適用します。もう一つの手法である原価法は、市街地に存する場合には、適用できないことが多い為、2手法となります。
この場合に、本来であれば、2手法を適用しなければいけないのに、取引事例比較法のみを適用する、ということになりましたら、「不動産鑑定評価基準」に則っていないことになります。
そうしますと、「鑑定評価書」とすることは出来ず、「調査報告書」となります。

②机上での査定
もう一つの例ですが、机上での査定を例にあげます。
鑑定評価では、現地調査が必須となります。これは当たり前なのですが、現地に行くなければ、評価する不動産が、そもそも存在するのか、どのような状態にあるのか分からないからです。
ですので、現地に行かずに机上で査定をする、ということになりましたら、「不動産鑑定評価基準」に則っていないことになります。

③簡略化
2つの例をあげましたが、この2つには共通するところがあります。
どちらも、本来の鑑定評価よりも簡略化しているということです。
①の場合であれば、2手法適用することが出来るのに、1手法しか適用していません。②の場合には、現地を確認すればいいのに、それを省略しています。
要するに、「鑑定評価書」を簡略化したものと考えていただいて、概ね間違いはありません。
なお、少し専門的な説明になりますが、「調査報告書」でも、異なる観点から「調査報告書」としなければいけない場合があります。
「不動産鑑定評価基準」に則りたいのだけれども、則ることが出来ない場合です。
例えば、過去時点の鑑定評価が、これに該当する場合があります。
評価する不動産が建物も含む場合に、その建物が現時点で取り壊されていたとしましょう。
そうしますと、建物を確認することができませんので、「不動産鑑定評価基準」則ることができません。このような場合にも、「調査報告書」となります。
以上まとめますと、「調査報告書」には、2種類あることになります。1つは簡略化したものです。もう一つは、やむを得ず「鑑定評価基準」に則ることが出来ないもの、の2種類です。
この2つの違いをもう少し詳しく説明しますと、簡略化したものの方は、必要最低限の記述に留まることが多いです。もう一つの方は、「鑑定評価基準」に則れない部分以外は、「鑑定評価基準」に準拠していますので、タイトルは「調査報告書」となっていても、実質的な内容は「鑑定評価書」とほぼ変わらないことが多いです。
(3)意見書
最後に意見書です。
不動産鑑定評価上は、「不動産鑑定評価基準」に則っているかどうかが問題になり、則っていれば「鑑定評価書」、則っていなければ「鑑定評価書ではない」ということになります。
つまり、「鑑定評価書」については、定義されていますが、「鑑定評価基準」に則っていないものについては、「鑑定」、「評価」などの文言は使用してはいけない、とあるのみで、それ以外の定義はありません。
本ブログ中で、「調査報告書」、「意見書」という用語を使用していますが、これらの違いについては定義はないということになります。分かるのは、「不動産鑑定評価基準」に則っていない、ということだけです。
ですので、各不動産鑑定業者によって、「調査報告書」、「意見書」が何を指しているのかは異なってきます。これは、確認するしかありません。
例えばですが、ある鑑定業者は、「意見書」としていて、別の業者は「調査報告書」としていて、タイトルは異なりますが、内容は同じ、ということも考えられます。
そこで、弊社の場合ですが、弊社では、「調査報告書」と「意見書」は、内容の違うものとなっております。
ここでは、詳細説明は省きますが、「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」と称する)というものがあり、価格を算出する場合には、「鑑定評価基準」に則っていようが、いなかろうが、このガイドラインの対象となります。
「鑑定評価基準」に則ってはいないが、このガイドラインの対象となるものを、弊社では「調査報告書」と、ガイドラインの対象とならないものを「意見書」としています。
先に、価格を算出すると述べました。そうしますと、意見書は価格を算出しないものとなります。価格を算出しないとは、どういうことでしょうか。
例えばですが、変動率を求めるとか、格差率を求めるとか、直接的に価格を求めないもの、ということになります。
弊社では、このように、直接的に価格を求めないものを「意見書」としています。
そうしますと、「意見書」となることは稀で、たいていの場合は、「鑑定評価書」か「調査報告書」になるということになります。

2.どれを選択すればいいのか
どれを選択するのかですがですが、大別すると2つに分けられます。
不動産の価格を知りたいという時には、通常、なんらかの目的がある筈です。
ですので、その目的に沿う選択になります。
以下、分かりやすいように説明しますが、状況によっては難しい場面もあります。ご自身で判断なさらず、不動産鑑定士に相談することをお勧め致します。
対外的な使用(鑑定評価書)
簡単に言ってしますと、どこかに提出するか、誰かに見せるか、ということです。
例外的に、提出先の承諾が得られているような場合には、後述する「調査報告書」でもいい場合があります。
内部での使用(調査報告書)
先とは反対に、提出もしない、社外の人などに見せることはない、ということになります。
このような場合には、調査報告書でもいいでしょう。
なお、先に説明させていただいておりますが、「調査報告書」は簡易的なものとなりますので、精度を追求したい場合には、「鑑定評価書」とすることをおすすめします。
「鑑定評価書」はどんな場合にも活用することが出来ます。
